大石内蔵助は江戸時代前・中期の武士で播磨藩の筆頭家老です。
大石内蔵助の家族には誰かいるのでしょう。
大石内蔵助の子孫や年収も気になるところですね。
大石内蔵助の家族や子孫、年収について調べてみました。
大石内蔵助の子孫は5人で家系は続いているのか?
大石内蔵助には5人の子どもがいます。
- 長男 主税(享年十六歳)
- 長女 クウ(享年十五歳)
- 次女 ルリ(享年五十三歳)
- 次男 吉千代(享年十九歳)
- 三男 大三郎(享年六十九歳)
- 次男 吉千代のち吉之進累罪を恐れた石束家一門は元禄十五年六月に松平伊賀守領分の但州美含郡竹野谷の順谷村井山にある円通寺の大休和尚の許で出家します。元禄十五年十月に剃髪し「祖練(錬)元快」と名乗るが大赦令の出た直後の宝永六年(1709)三月一日に十九歳で入寂。
 NHK好き男性(田中正吉)
NHK好き男性(田中正吉)興国寺に葬られましたが興国寺が廃寺となり正福寺のクウの墓域に移されていますね。
豊岡城主京極甲斐守からの元禄十六年二月五日の公儀届書に「内蔵助妻去年十月初旬離別、吉之進母離別前より出家」とあり、大石内蔵助は吉千代の将来について、討入りの前々日に赤穂の恵光・良雲・神護寺の三僧に宛てた暇乞状の中で吉之進の出家を残念がり「一度武名之家をおこし候様に支度事に候」と書いています。
三男 大三郎のち代三郎
元禄十五年(1702)七月五(七)日に豊岡石束家で生まれる。
 NHK好き主婦(三村和子)
NHK好き主婦(三村和子)百日余りで石束家の家来雲伝(くもで)茂兵衛の養子となりその後、生後六ヶ月で宮津の眼医者林文左衛門が金子十両を添えて実子として貰い受けていますね。
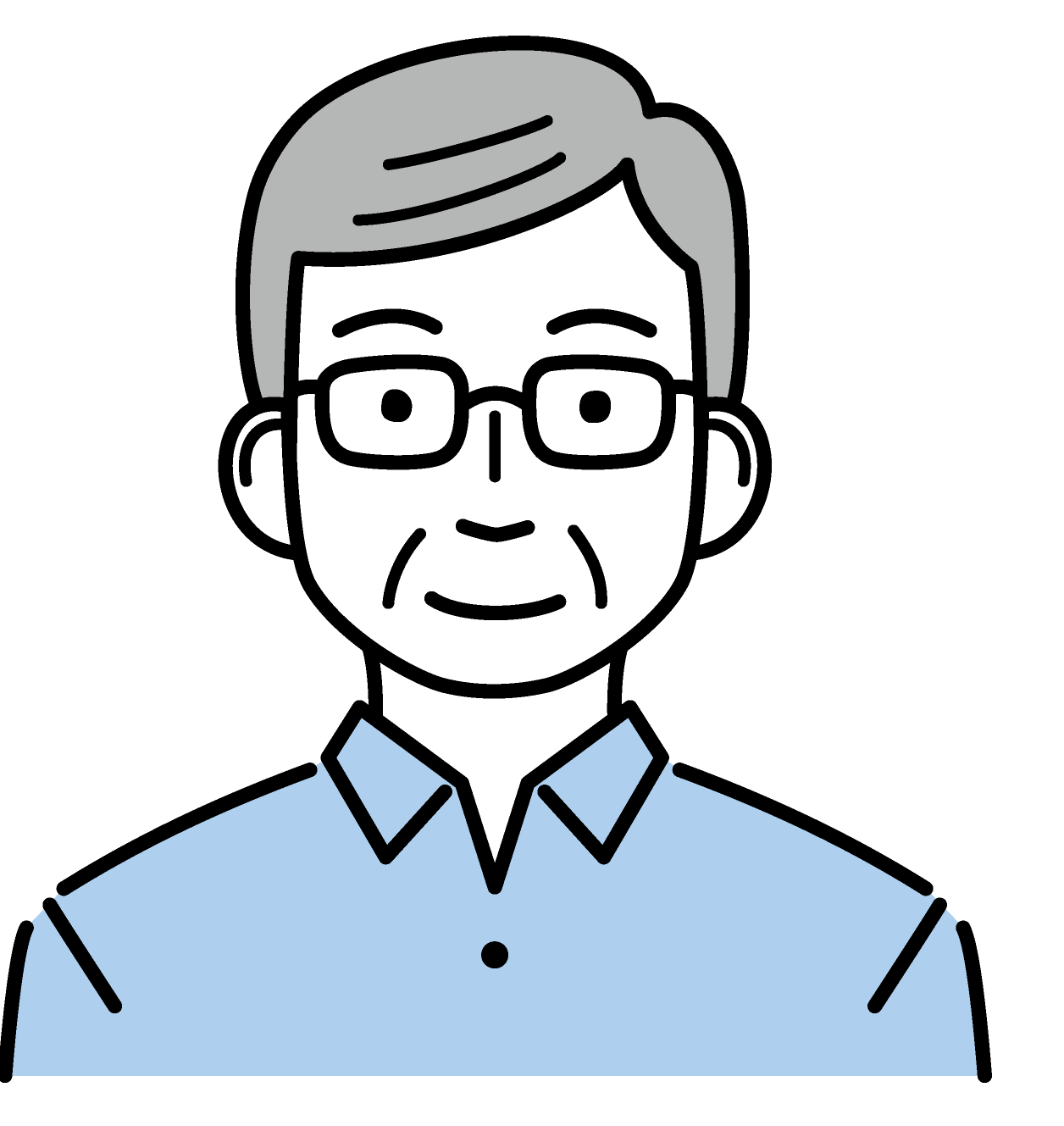 NHK好き男性(藤村茂)
NHK好き男性(藤村茂)幕府は遺子の探索で、大三郎を林文左衛門の実子としては認めず内蔵助の三男とした為、再び石束家に引き取られています。
- 宝永六年(1709)の大赦により免罪となり晴れて大石内蔵助の跡取りとして成長します。
- 正徳三年(1713)九月二十六日に芸州浅野家の招きで千五百石の知行で召し抱えられます。時に十二歳でした。
- 享保二年(1717)十六歳で元服し大石外衛良恭と名乗ります。
- 享保六年(1721)九月十九日に家中五千石年寄役浅野帯刀の娘と結婚し初め旗奉行次席、次に番頭、表番頭を歴任し明和五年三月十八日に六十七歳で隠居を願い出ます。
 NHK好き主婦(鈴村春子)
NHK好き主婦(鈴村春子)明和七年(1770)二月十四日六十九歳で広島で没し、墓所は国泰寺で戒名「松巌院忠幹蒼栄居士」です。
長女 くう
 NHK好き主婦(笹木たえ)
NHK好き主婦(笹木たえ)宝永元年(1704)九月二十九日十五歳で病没し但馬豊岡日撫正福寺裏山に埋葬されました。
次女 るり一時期、進藤源四郎の養女となるが理玖が豊岡に帰る時に戻され、大三郎が正徳三年(1713)に安芸広島藩に仕官する時に母と共に広島に移ります。
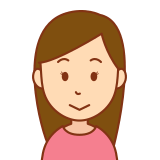
その後藩主浅野吉長の命で十六歳の時、安芸広島藩家臣浅野長十郎信之(後の監物直道)の妻となり二男四女をもうけていますね。
宝暦元年(1751)六月に五十三歳で死去。
墓所は常林院で戒名は「正聚院定譽寿真大姉」です。
 NHK好き男性(田中正吉)
NHK好き男性(田中正吉)母と子が受けた本家浅野での厚遇は大石内蔵助親子の忠義に報いるためであったに相違ないと思われます。。
大石内蔵助の子孫はどの家系に分かれている
討ち入りから6年後の宝永6年(1709)に将軍が綱吉から家宣に代わります。その恩赦で義士の遺子たちは免罪となります。
この時点で次男・吉之進と長女・くうは若くして亡くなっています。
 NHK好き男性(田中正吉)
NHK好き男性(田中正吉)これにより、良雄の男子でただ一人生存していた大三郎を広島藩浅野本家が家臣に迎えようとします。
 NHK好き主婦(笹木たえ)
NHK好き主婦(笹木たえ)浅野本家としては、世間に人気がある大石内蔵助の息子を家臣に欲しがったということなのですね。
正徳3年(1713)9月に大三郎は広島藩に仕官が決まり、父と同じ知行1500石で召し抱えられ、広島城二の丸の屋敷を与えられています。
母・りくと姉・るりも一緒に広島へ移り住みました。
享保2年(1717)、大三郎は16歳で元服し大石良恭(よしやす)と名乗ります。
 NHK好き主婦(三村和子)
NHK好き主婦(三村和子)享保6年(1721)には藩主浅野吉長の命により浅野一族の娘と結婚しており、厚遇されていたことがわかりますね。
 NHK好き主婦(笹木たえ)
NHK好き主婦(笹木たえ)良恭は生涯3回結婚して、その内の二人は浅野一族の娘でしたが、いずれも離縁していますね。
姉・るりは浅野家の一族浅野直道に嫁いで53歳で亡くなっています。
良恭は、広島藩内において旗奉行次席・番頭・奏者頭などの重職についています。
良恭は、明和5年(1768)に隠居します。
 NHK好き主婦(鈴村春子)
NHK好き主婦(鈴村春子)男子が二人いましたが、いずれも妾が生んだ子であったためなのか、なぜか実子に跡を継がせませんでした。
 NHK好き主婦(三村和子)
NHK好き主婦(三村和子)同じ広島藩士の小山家から良尚(よしなお)を婿養子に迎えて大石家の家督を継がせました。
この時、知行が1500石から1200石に減らされています。
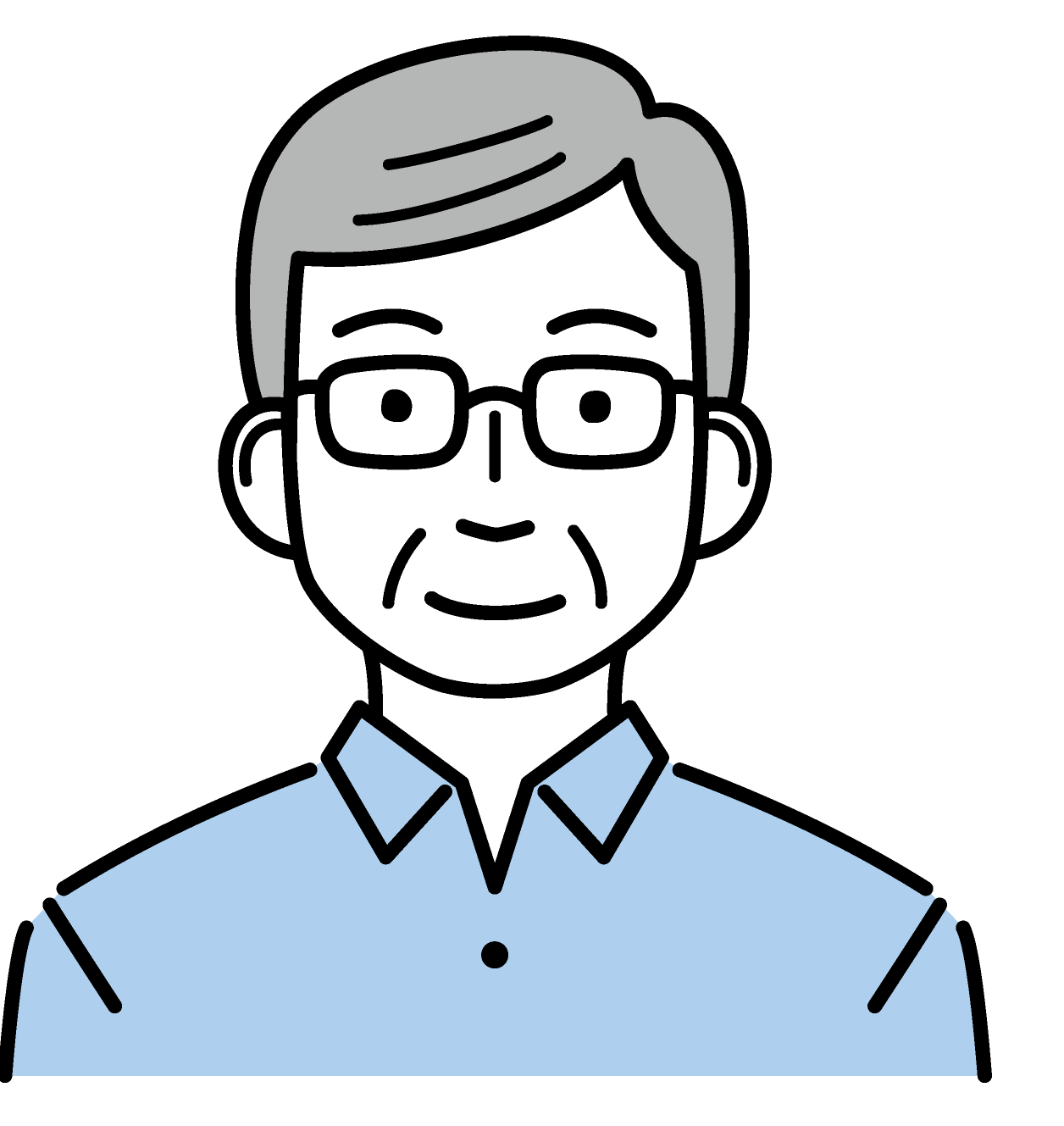 NHK好き男性(藤村茂)
NHK好き男性(藤村茂)養子に迎えた良尚の曽祖父・良速(よしずみ)は、父・良雄の叔父で小山家に養子に入った人物です。
 NHK好き主婦(三村和子)
NHK好き主婦(三村和子)大石家と小山家は元々親戚関係だったのですね。
良尚は、嫡男に早くに先立たれて、寛政9年(1797)には大石家を去って、実家の小山家に帰って亡くなっています。
大石家は断絶となりますが、寛政9年、良恭の庶子で横田家に養子に入っていたとされる良遂(横田正虎)の次男温良が大石に改姓し、500石を与えられます(横田大石家)。
明治維新時に、新政府が泉岳寺で赤穂浪士を顕彰し祠堂を造営した際は、広島藩知事浅野長勲の命により、当時の横田大石家の当主大石良知が、所蔵していた良雄の木像を泉岳寺まで持参しています。
 NHK好き男性(田中正吉)
NHK好き男性(田中正吉)横田大石家も、明治23年(1889)の良知の死により断絶したといわれています。
大石内蔵助の子孫はどの程度の血統が続いている?

嫡男の大石良金は内蔵助とともに吉良邸への討ち入りに参加し、切腹となりました。
のちに三男の大石良恭が家督を相続しますが、その次の代からは養子の小山氏、さらに次代も養子の横田氏と転々と継承されていきました。
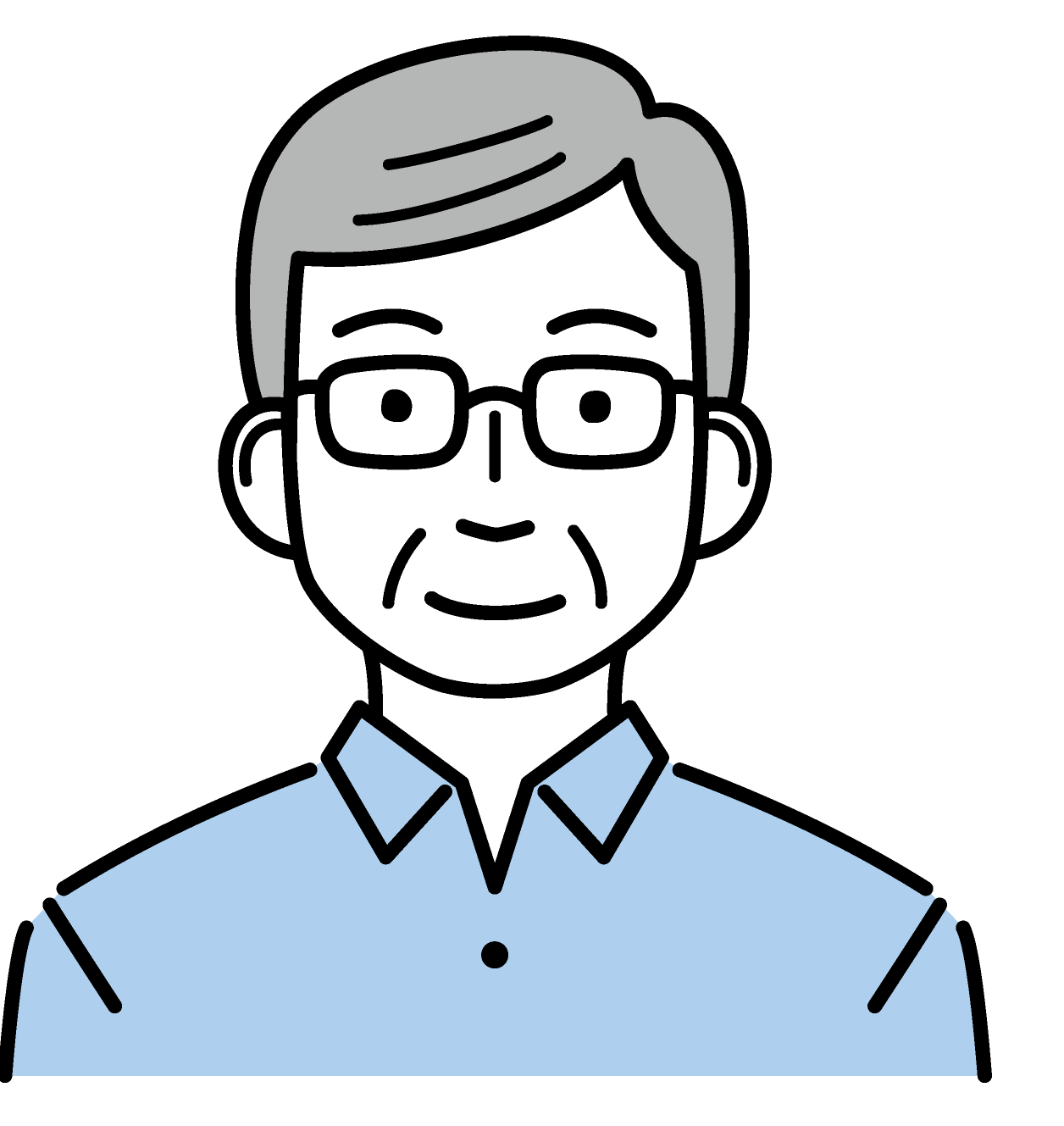
大石良恭には少なくともふたりの実子がいたとされています。

歴史に書き記されてはいないものの、どこかで大石内蔵助の血脈が受け継がれ続けているかもしれませんね。
大石内蔵助の仕事や年収は?偉人の年収houmuch?
大石内蔵助大石 良雄(おおいし よしお / おおいし よしたか、万治2年〈1659年〉- 元禄16年2月4日〈1703年3月20日〉)は、江戸時代前・中期の武士で播磨赤穂藩の筆頭家老です。

若くして領地と「内蔵助」の通称を受け継ぎ、21歳で赤穂藩の筆頭家老という重職に就いています。
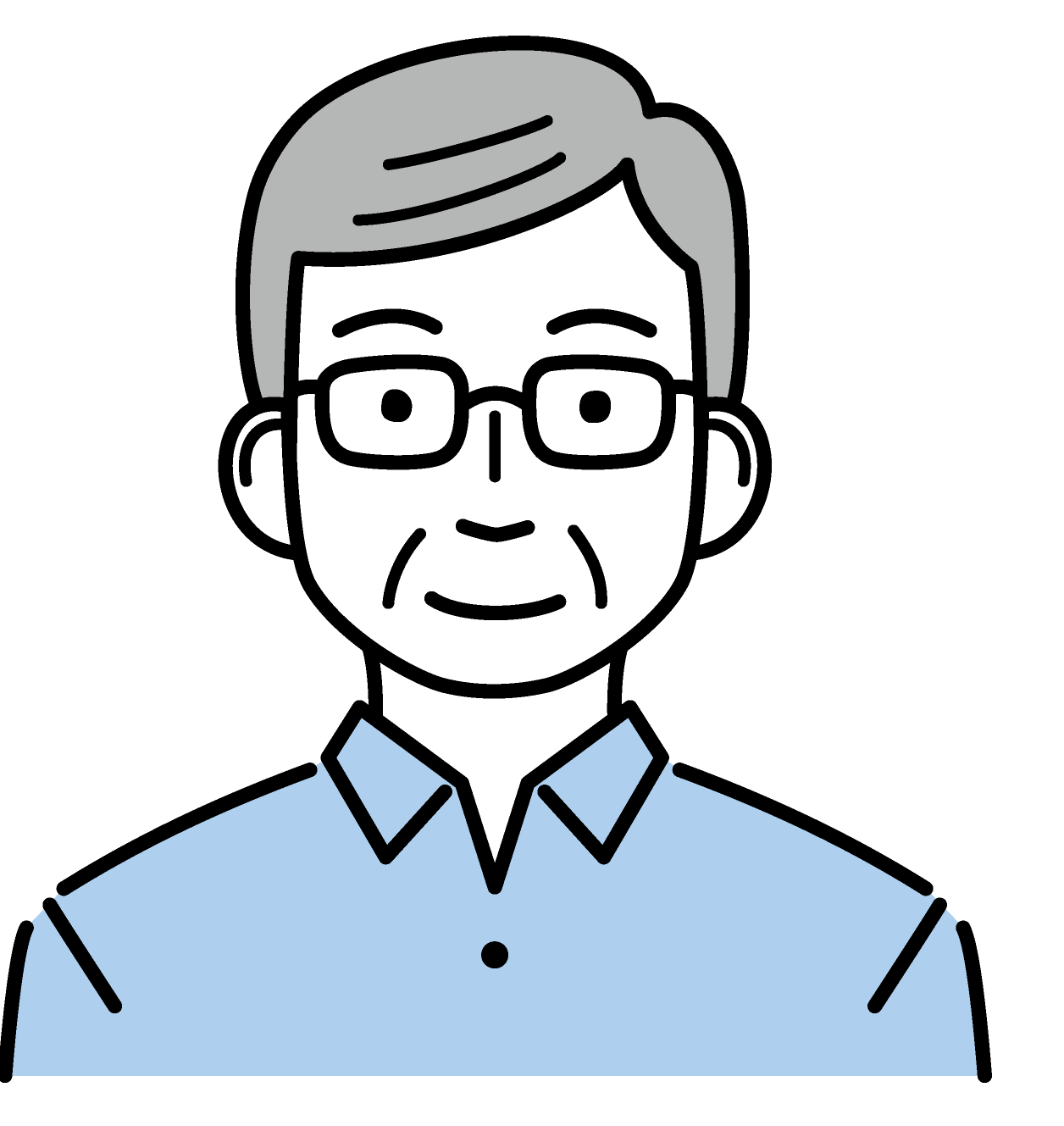
知行は1500石で、現代ですと年収5000万円といったところではないでしょうか
何事も無ければこのように安定した生活が保障されていました。
江戸時代の中頃に入った1701年、主君・浅野内匠頭(浅野長矩)が、江戸城内の松の廊下にて、上役とも言える吉良上野介を短刀で刺す「殿中刃傷事件」を起こします。

江戸城内で刀を抜くことは禁止されていたこともあり、徳川将軍・徳川綱吉や柳沢吉保は、浅野内匠頭を異例の即日切腹としています。

赤穂藩は取り潰し(領地没収)となり、大石内蔵助ら藩士も浪人となってしまいました。
江戸城松の廊下で刃傷に及んだ赤穂藩主浅野内匠頭が切腹に処せられ、藩は解散して財産を没収されることになります。
大石内蔵助の家系図は?
大石内蔵助の家系図を見てみると、父方の大石氏は藤原北家秀郷流とされますが、系図を遡れるのは室町時代後期くらいまでで定かではありません。

内蔵助より4代先祖の大石良信は、関白・豊臣秀次に仕えたとされ、その息子の代から浅野家に仕えるようになりました。
母方は池田氏の出身で、織田家重臣・池田恒興の子孫です。
池田氏は紀貫之などを輩出した紀氏の末裔を称しており、これを事実とするならばその系図は古代にまで遡ることができます。
父:大石良昭
妻:理玖(りく)(現豊岡市出身。豊岡京極家の家老・石束宇右衛門(毎公)の娘)
子供
- 長男 主税(享年十六歳)
- 長女 クウ(享年十五歳)
- 次女 ルリ(享年五十三歳)
- 次男 吉千代(享年十九歳)
- 三男 大三郎(享年六十九歳)

妻の理玖(りく)は豊岡京極家の家老・石束宇右衛門(毎公)と、佐々成政の子孫・快楽院の長女として生まれました。
三男の大三郎は、妻の理玖や子らは罪が連座しないように絶縁されて山科から豊岡に戻されます。この時りくが妊娠しており、豊岡で出産することになります。そして生まれたのがこの大三郎です。

赤穂の浪士たちの行為は人々に感銘を与え、理玖や大三郎が有名になると赤穂浅野家の本家にあたる広島から仕官の話が舞い込みます。
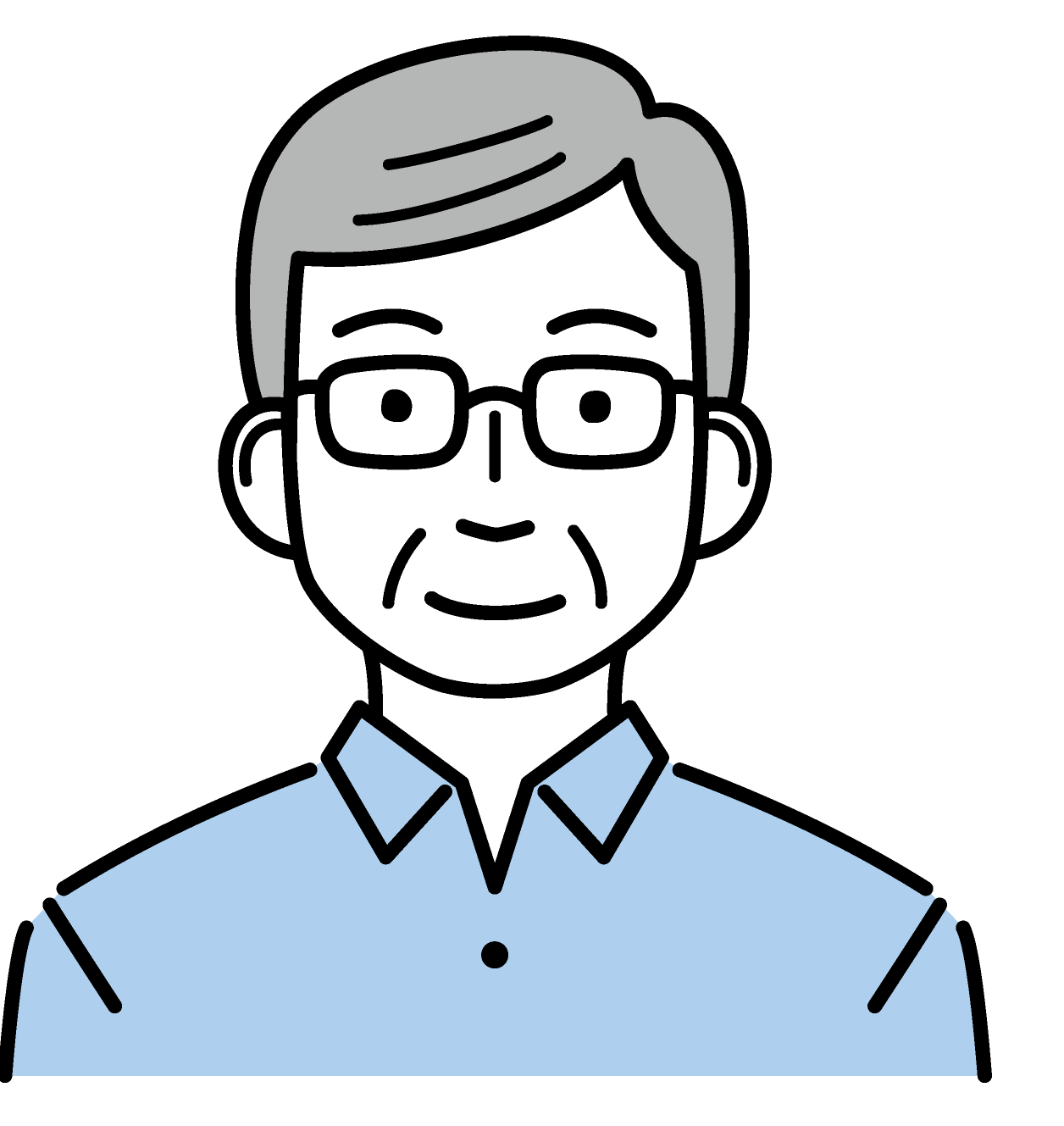
大三郎は父・良雄(内蔵助)と同じ1500石という破格の条件で召抱えられ、理玖と一緒に広島へ移ります。
略歴・経歴(プロフィール)
■大石良雄(おおいし・よしお)
■一般的には大石内蔵助(おおいし・くらのすけ)の名で広く知られる
■江戸時代前期の武士
■播磨国赤穂藩の筆頭家老
■赤穂事件で名を上げ、これを題材とした人形浄瑠璃・歌舞伎『仮名手本忠臣蔵』で有名になった
■身長:157cm程度だと言う
■頭蓋骨の調査でこめかみの筋肉と下顎が発達していたことから庶民的な顔つきだったようである
大石内蔵助の直系の子孫は主に豊岡と広島に住まいを構えていた!
大石内蔵助の妻、りくの手紙
大石内蔵助の子供にはちから以外にも2人の息子がいます。

大石内蔵助から11代目の大石浩史さんがいらっしゃいます。
大石内蔵助の子孫はどの程度の歴史的記録を残している?
大石大三郎は大石内蔵助の三男で元禄十五年(1702)七月五(七)日に豊岡石束家で生まれる。
大石大三郎は大石良恭と改名します。

良恭は養子良尚を迎えますが後継者となった男子が先立ち大石家は断絶していますね。
大石内蔵助が管理した資金は約690両(現在の価値で約9660万円)!

この後始末を担当したのが討ち入りの首謀者である赤穂藩家老大石内蔵助です。
内蔵助は、藩が所有していた米や船などの資産を売り払ってお金に換え、藩士への退職金として分配しますが、主君の仏事費やお家再興の資金として七百両ほどを手元に残します。
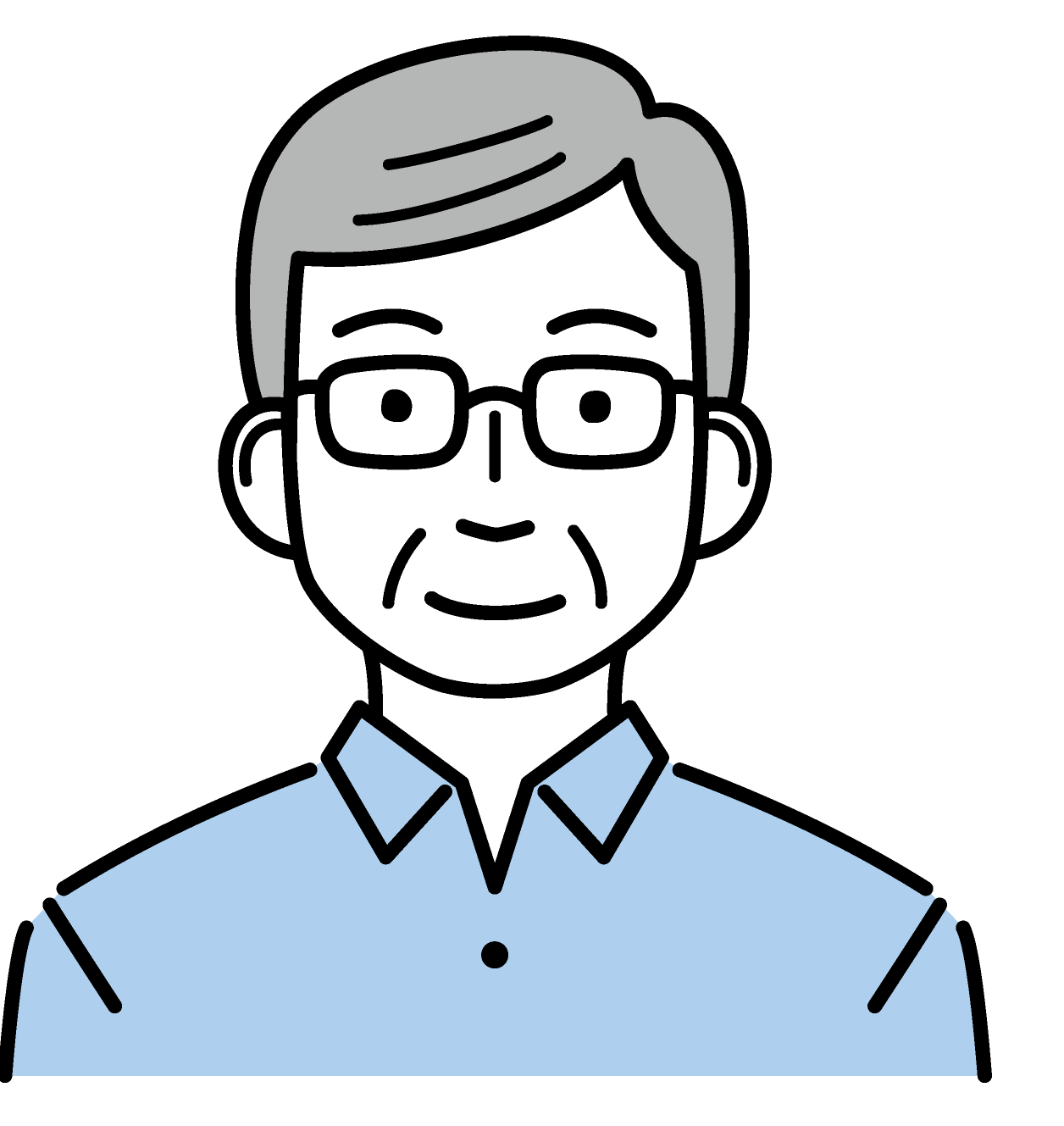
一両を十万円として換算すると七千万円ということになり、結構な大金であることは間違いありませんね。

これが結局は討ち入りのための資金として使われることになります。
実は大石は、このほかにもいろいろな帳面をつくっていて、そのリストを討ち入り前に赤穂藩主浅野内匠頭の妻である瑤泉院に渡したため、どんな帳面をつくったかはわかっているのですが、帳面そのものはすべて散逸してしまっていました。
それが、明治時代になって『預置候金銀請払帳』が箱根神社に奉納されたため、現在でもこの帳面だけ現物が残っているわけです。
この帳面には、当然のことながら当時の物の値段が克明に記録してあって、歴史的にも非常に貴重な史料です。そこで、ここでは、『預置候金銀請払帳』に記録されている、いろいろ
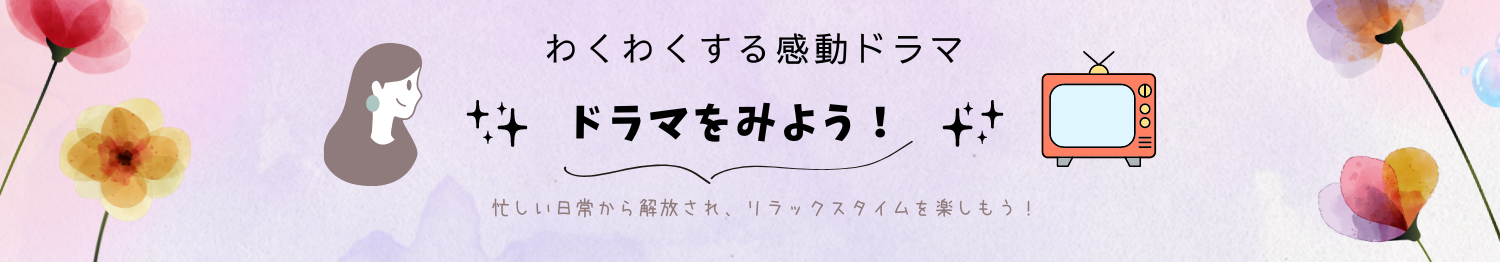
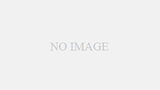

コメント